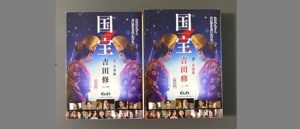157.続・マイナ保険証をつかってみた
先週のコラム「マイナ保険証をつかってみた」をWEBに公開した日にも病院に行きましたが、そこにあったカードリーダーもこれまでのものとは違うタイプでした。
5種類目!
「一体何種類あるのだ?!」と改めて思っていたら、その日(7月28日)の日本経済新聞に「現行5機種」という記事を見つけました。私は、早くも全機種を制覇したようです。
さて、その日経新聞の記事のタイトルは、
「「スマホ保険証」混乱の恐れ 9月の開始控え、iPhoneマイナ対応で」
一部を抜粋すると、
スマートフォンを健康保険証として使う「スマホ保険証」の9月開始を控え、医療現場に混乱の恐れが出ている。医療機関が読み取り機器を準備する必要があるのに政府は対応状況の実態すら把握していない。米アップルのiPhoneが6月にマイナンバーカード機能の搭載に対応したことで開始前からスマホだけ持参する患者も出ている。
医療機関はマイナ保険証向けの顔認証付きカードリーダーとは別に新たな機器の購入が必要なケースが多いとみられる。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA144GE0U5A710C2000000/
やはり、カードリーダー以外にスマホ保険証対応のリーダーが導入されるか更新される
記者(編集者)は、カードリーダーの種類が多いことを問題にはしていない・・・
そもそも通院している人の多くは高齢者です。変化や新しい仕組みに対応が難しくなり拒絶反応しがちです。なによりも病院に行く人は当然身体のどこかの具合が悪い、精神的にハッピーな状態ではなく、イライラしています。その人たちにさらにストレスを与える、余分な手間をかけさせることは好ましいことではありませんよね。マイナ保険証やスマホ保険証を推奨するのであれば、社会インフラを速やかに「単純で分かりやすい形」に整備しておかなければなりません。
さて話はがらっと変わります。
中央線快速にグリーン車両が新たに導入されましたが、乗車している人の姿はほとんどなく空気を運んでいる状態です。試しに乗ってみようかとホームのグリーン券売機の前に立って唖然。Suica、PASMOなどの「カード」でしか購入できない、つまりスマホ対応になっていないのです。
調べてみるとモバイルSuicaならアプリからグリーン券を購入できるようです。しかし、モバイルPASMOのアプリからは当然のことながら購入できず、一度改札を出て、券売機で磁気グリーン券という紙?の切符を購入する必要があります。つまりモバイルPASMOユーザーは実質JRのグリーン車の対象外、排除、乗らなくていいよということです。
これまた驚きです。
モバイルSuicaやモバイルPASMOの利便性をさんざん宣伝しているにも関わらず、なんと中途半端なことでしょう!?モバイルPASMOによるJRグリーン券購入のシステムにどのようなハードルがあるかは知りませんが、そんなに難しいことなのですか?
それともJRのモバイルSuica拡販の戦略なのでしょうか?
そうだとしたら、ちょっとビジネスセンスが悪いですよ・・・