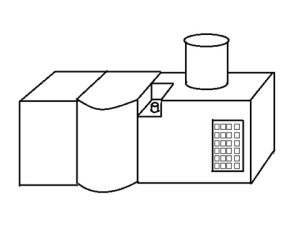145. 老舗料亭の出汁の分析
私がいた味の素社では、味覚の鋭い人を選ぶ選抜試験が入社後すぐにあります。合格すると、新製品などの味を評価するパネラーとなり、認定書とバッチが渡されます。当時は作業着のある時代でしたから、合格者はバッチを勲章のように胸につけていまいた。
その試験は何項目かに分かれているのですが、例えば、その味を感じるか感じないかギリギリの濃度(閾値)の溶液を口にして、それが5味(甘味、塩味、酸味、苦味、うま味)のどれかを当てるテストです。子供の頃から食べ物の好き嫌いが多かった私は、味覚は鋭いはずと自信満々で試験に臨んだのですが、それは全くの錯覚、単なるわがままであったことが入社早々に思い知らされました。
これにはさらに後日談があり、研究所長になって同様の試験を受ける機会がありました。例題として出された「真水」と「うま味を少しつけた水」の区別がつかず、つまり真水をうま味と答えてしまい、担当者に嘲笑気味(と私は感じた)に笑われた、それこそ「苦い」経験があります。
私の味覚音痴には関係していないと思うのですが、会社生活では食品の分析に携わることは多くありませんでしたが、いくつかの記憶に残る仕事がありました。
その一つに、有名な料亭の出汁の成分を分析があります。
昆布やかつおなどから出汁をとるのですが、その原料(○○産のいつ採れた昆布とか)や工程(量、温度、時間など)はその料亭に伝わる独自ものがあります。どのタイミングでどういう成分が抽出されているのか?それぞれに特徴があるのか?京都や築地の有名な料亭からサンプルをいただきました。「サンプルをいただき」と書きましたが、私の同僚が出汁をとる場に同席して、工程ごとにサンプリング→急冷(冷凍)→クール宅急便で研究所に送付、と測定までにかなり労力のかかる作業でした。
私が驚いたのは、その料亭のいわゆるご主人の方々が、この分析・解析に大変関心をもってくださったことでした。付き合いのある味の素社さんだから協力しよう程度のお気持ちなのだろう、自分たちの舌が全てだと考えていらっしゃるのだろうと、私は勝手に思っていたのですが、出汁の科学的な解析結果をまさに食い入るように聞いてくださったのが印象的でした。
菊乃井三代目主人村田吉弘さんの近著「ほんまに「おいしい」って何やろ?」にこんな一節がありました。
「京料理も「伝統」やら「親から子へ」やらはちょっと置いといて、一度「科学の光」を当ててみるのもおもしろいかもしれん。何か、我々が知らなかったことが浮かび上がるかもしれん。そこに危機脱出のヒントが得られるかもしれん。(中略)
京料理全体を学問的に、文化的に位置付けし直すとともに、科学的アプローチでその味と技術の本質を明らかにしてみよう、という方向性を得て、「日本料理アカデミー」という団体を作ることになったのです。 」
(第二章 料亭、料理屋、料理人って何や?66頁より引用。)
https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-781759-1
あらためて、当時のことを思い出しました。
自分たちの料理と味の特徴や受け継いできたものを科学に捉えることに大変興味を持ち、歓迎されてくださり、話を聞いてくださったみなさんの真摯な姿に感銘を受けた仕事でした。