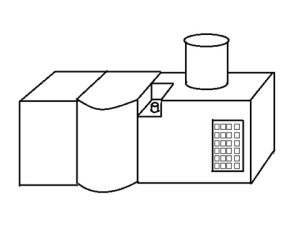146. 同世代が集まると年金の話になります
先日、大学時代のサークルの同期(±1年)会が東京大学の駒場キャンパス内のレストランでありました。
「139.それぞれの春 その1 新しく大学生になる方へ」で最終講義の紹介をした物理の先生もいたサークルで「点友会」といいます。「点」は「点字」のことで、目の不自由な人達が読めるように点字に翻訳することを目的としたボランティアサークルで、今も活動しているようです。
同級生のその後の経歴、社会での活躍はいろいろです。
駒場キャンパスを歩いていると必ずといっていいほど学生に挨拶される人がいます。某有名進学校の教師で、声をかけるのは元教え子たちです。彼といると東大進学者数NO1の高校の勢力?!の凄さを実感できます。
書籍を出している人も何人もいます。
そのうちの一人は、私たちの世代の会長でしたが、残念ながら60歳を前に病気でなくなりました。福祉、医療、教育、特に出生前診断の問題をライフワークにしていて、存命ならその分野の政策提言などに影響力を発揮していたはずで、とても残念です。
10年近く前に「2025年に社会保障のクライシスがくる」という内容の本を出したシンクタンクの元研究員がいます。そう、今年の預言書で、2025年とは団塊の世代が後期高齢者になる年だそうです。(初めて知りました。)本人曰く、「ザイム真理教」信者の立ち位置で書いていたと笑っていました。
集まった人たちは皆64~65歳なので、年金をいつからもらうか、ということが話題となります。厚労省が繰り下げたほうがお得、つまり65歳よりも遅らせて受け取ったほうが生涯年金額は多くなるという宣伝をさかんにしていますが、彼の見解は以下の通りでした。
「損益分岐点を平均余命において年金は設計されている。
繰り下げてもいいが、平均余命を超えて生きていないと逆に総額は少なくなる(損をする。)
平均余命くらいは生きれるだろうと多くの人が思っているが、「平均」なので半数はその年齢前に死んでしまうことを頭に入れておかなければならない。」
この年齢分布が正規分布ではないでしょうから、必ずしも平均=半分ではないとは思いますが、言われてみれば確かにそうです。
先日の日経新聞によると、2022年の平均寿命は男性81.05歳、女性87.09歳。(寿命と余命はちがいますが・・・)健康寿命は男性72.57歳、女性75.45歳とあり、健康の定義はよく理解していませんが、その年齢までにざっくり半数の方が、なんらかの疾病や障害をもつことになります。
健康なうちにちゃんと年金をもらって使うほうがいいかもしれません。
彼の結論も、「もらえる時にもらっておこう」ということでした。