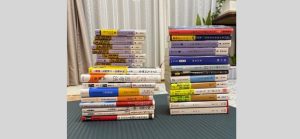165. 製造業の分析技術と特許
とてもニッチな話題ですが、製造業で分析化学を研究している方にはとても大事なお話で、その人たちへのお願いでもあります。
分析技術は、製造業の研究開発にとっても重要な役割を果たしています。独自性が高く優位性のある分析によって他社に先んじた発見があり、そこから高性能、高付加価値のある製品が生まれます。また、その製品の品質は高い分析技術力によって最終的に保証されます。
優れた分析技術や方法について、特許性のあるものが多いはずです。
特許すなわち発明には3つの要素が必要です。
1.その発明が産業活動に利用できること(産業上利用可能性)
2.出願時点で公知または公用でないこと(新規性)
3.そして先行技術から容易に思いつかない高度なものこと(進歩性)
分析研究に携わる人たちは謙虚なのか、自分たちの方法・技術は先行技術から誰もが容易に思いつくものだ、つまり進歩性がないと考えがちです。
しかし、私からみればそれはあなたの「個人の見解」です。あなたが判断することではありません。
特許性があるかないかを決めるのは特許庁の審査官です。
そして特許庁に出願するためには、まず自社の知的財産部門に特許性があると認めてもらわなければなりません。残念ながら、分析に関する特許出願に積極的な製造業は皆無です。特許登録や国際出願の費用はバカになりませんので、どうしてもモノづくりに直接関わるものが優先されます。
繰返しになりますが、その分析方法・技術があってこそ、新しい製品が生まれ続けます。
仮に他社が類似の方法を出願し特許として認められてしまえば、自分たちはその方法が使えなくなる、制限される、ライセンス料を支払う、特許を潰すための膨大な作業量が必要となる・・・、自分たちと会社は不利益をこうむりかねません。自分たちの特許にしてしまえば、その逆のことがおこります。また、その方法の有用性が思いもかけない第三者に認められて、ゆくゆくライセンス料が入ることもあります。
製造業で分析研究に関わる人たちは、世間で行われていない、公知になっていない、つまり自分たちだけの方法や技術が発明に当たらないかを貪欲に考えてください。知的財産を管轄する部門が納得する3要件を満たすストーリーを練りましょう。
また特許出願できたとしても、特許庁から必ずと言っていいほど拒絶理由通知が届きます。それでへこたれてはいけません。しっかりと反論していきましょう。